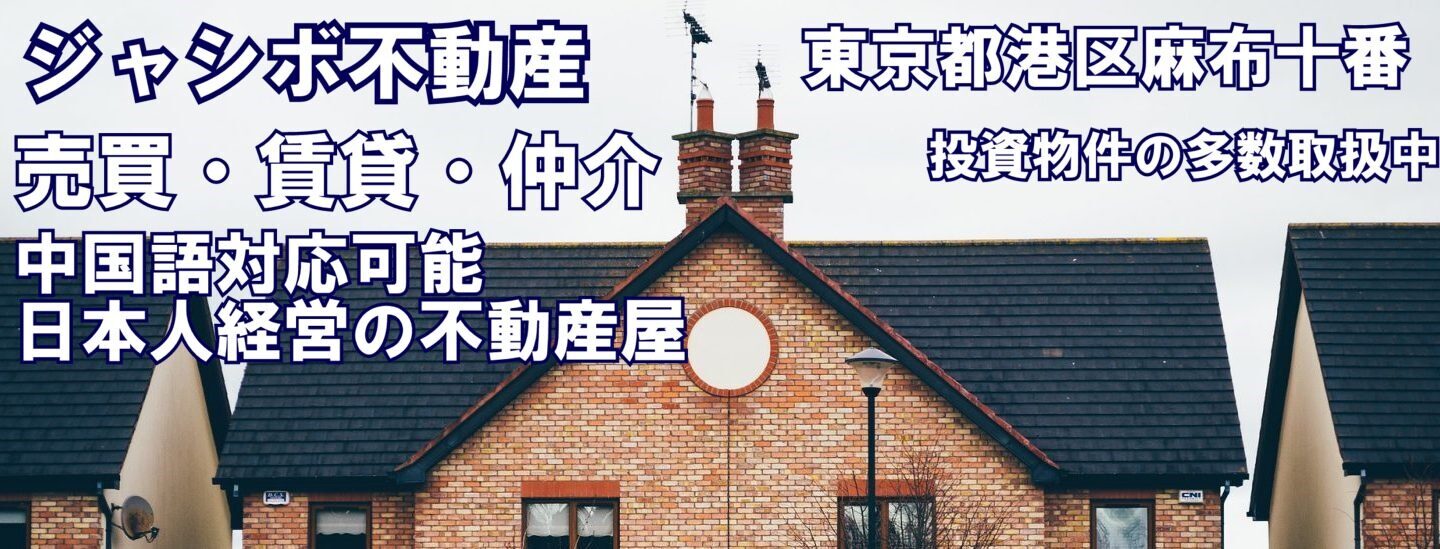1. 原状回復とは
(1) 定義
原状回復とは、賃貸借契約終了時に、借主(テナントや居住者)が物件を返却する際に借主の使用によって生じた損耗や変更部分を元の状態に戻すことを指します。
ただし、元の状態とは「借りた当時の状態に完全に戻すこと」ではなく、通常使用による経年変化を除いた状態にすることを意味します。
(2) 法律的根拠
原状回復の義務は民法に基づいており、特に次の条文が関係します。
-
民法第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃貸借が終了したときは、賃借物を原状に復して返還しなければならない。
-
民法第622条の2(通常損耗・経年変化)
賃借物の通常の使用及び収益による損耗または経年変化は賃借人の原状回復義務に含まれない。
これにより、借主は故意・過失や特別な使用によって生じた損耗のみ修繕義務を負い、**通常損耗(生活で避けられない傷み)**は貸主の負担となります。
2. 原状回復をめぐるトラブル
(1) トラブルの多さ
国土交通省の統計によれば、賃貸住宅に関する相談の約4割が敷金返還や原状回復に関するものです。
特に以下のようなケースで争いになりやすいです。
-
借主が「普通に使っただけなのに修繕費を請求された」
-
貸主が「契約当初よりひどく汚されている」と主張する
(2) トラブル防止のための指針
国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(2021年改訂版)」を公表し、
貸主・借主間の費用負担ルールの標準化を図っています。
このガイドラインは法的拘束力はないものの、裁判所や実務でも参考にされます。
3. 費用負担の考え方
(1) 貸主負担(通常損耗・経年変化)
-
家具の設置による床やカーペットのへこみ
-
日焼けや経年によるクロスの色あせ
-
通常の生活で生じた軽微な汚れ
(2) 借主負担(故意・過失・特別使用)
-
タバコによるヤニ汚れや臭い
-
ペット飼育による傷・臭い(禁止物件で飼育した場合など)
-
飲み物をこぼしたことによるシミ、カビを放置したことによる腐食
-
無断での改造や造作の撤去
4. 原状回復に関する法令のポイント
(1) 民法(2020年改正)
2020年4月の民法改正により、原状回復の負担ルールが明確化されました。
-
借主は、通常損耗や経年変化を除いた損耗のみ負担する。
-
契約で特約を設ける場合は、借主に不利すぎない合理的内容でなければ無効となる可能性がある。
(2) 消費者契約法
-
借主が個人の場合、消費者契約法により「借主が通常損耗まで負担する」といった一方的に不利な特約は無効となる可能性があります。
(3) 賃貸住宅管理業法
-
管理会社が仲介や管理を行う場合、重要事項説明時に敷金・原状回復ルールを明示する義務があります。
5. 契約時に注意すべきこと
(1) 特約の確認
-
退去時のハウスクリーニング費用を借主負担とする特約は有効とされる場合が多いですが、明確に書かれていなければ無効と判断されることもあります。
-
契約書には「クロス張替え一式を借主負担とする」など曖昧な表現がないか確認。
(2) 入居時の現況確認
-
入居時に室内の傷や汚れを記録(写真撮影)しておくと、退去時のトラブル防止になります。
-
「現況確認書」にサインをして保管することが重要。
(3) 喫煙・ペット・DIY
-
禁止されている場合は必ず守ること。
-
禁止事項を無視すると大幅な修繕費請求につながります。
6. 貸主側の注意点
(1) 請求根拠の明確化
-
修繕費請求を行う際には、見積書や破損箇所の写真を用意し、負担範囲を明確化すること。
(2) 特約の適正化
-
消費者契約法やガイドラインに反しない内容で契約条項を定めること。
(3) 訴訟リスク
-
借主との交渉が決裂すると訴訟に発展する可能性があるため、ガイドラインに基づく対応が望ましい。
7. 退去時の流れ(居住用賃貸の場合)
-
退去日の立会い
-
室内確認(傷・汚れの確認)
-
修繕費用の見積り
-
敷金からの精算(不足分は追加請求、余剰分は返還)
-
明細書の交付
まとめ
-
原状回復義務は民法で定められており、通常損耗や経年変化は借主負担ではないという点が重要です。
-
契約書の特約や国交省ガイドラインを確認し、契約時・入居時・退去時に適切な記録と説明を行うことでトラブル防止につながります。
-
貸主も借主も法令とガイドラインを理解した上で、合理的かつ公平な費用分担を心がけることが求められます。