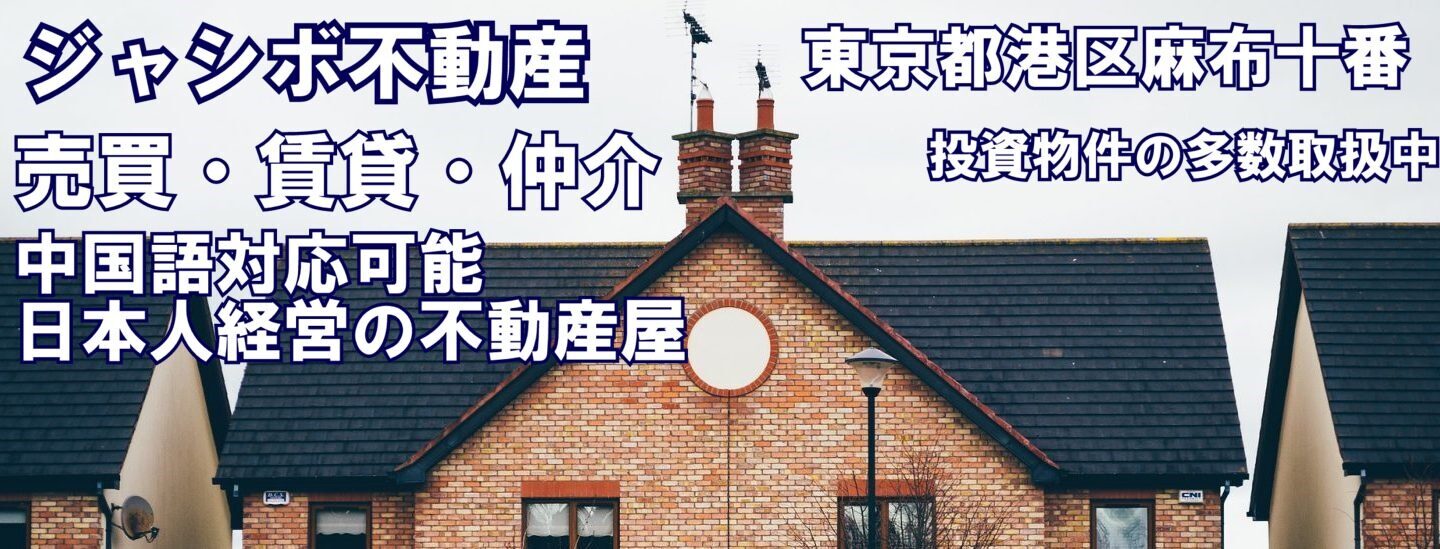不動産の購入は高額な取引であり、一度契約すると後戻りが難しいため、購入前に慎重な調査と判断が不可欠です。特に、建物の耐震性、敷地の法的条件、権利関係、そして売主のローン残債といった点は、購入後の安全性や資産価値に直結します。
1. 旧耐震と新耐震基準
建物を購入する際、まず注目すべきは耐震基準です。
-
旧耐震基準(1981年5月31日以前の建築確認)
震度5強程度の地震で建物が倒壊しないことを前提とした基準であり、現代の地震動を考慮すると十分でない場合があります。旧耐震建物は住宅ローンの利用や地震保険に制約が出る場合があり、耐震補強工事が必要になる可能性があります。 -
新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認)
震度6強〜7程度の地震でも倒壊・崩壊しないことを目標とした強化基準。住宅ローンや保険の審査でも有利であり、資産価値が高く保たれやすいのが特徴です。
購入する建物が旧耐震か新耐震かを確認し、旧耐震の場合は耐震診断や補強工事費用を検討に含めることが重要です。
2. 接続道路(建築基準法上の道路)
土地を購入する際は、その土地が建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接しているかを必ず確認します。
-
接道義務を満たさない土地は原則として再建築ができない、いわゆる再建築不可物件となり、資産価値や利用価値が著しく低下します。
-
道路の種類(公道か私道か)、私道の場合は通行権や持分の有無、道路の幅員や舗装状態なども調査が必要です。
接道条件が不十分な場合、リフォーム・建替えや将来の売却に制約が出るため、事前に法務局や市区町村での確認を怠らないことが重要です。
3. 境界線の明示
土地の境界線が明確であるかは非常に重要です。境界が不明確なまま購入すると、隣地とのトラブルや将来的な売却時に支障をきたす可能性があります。
-
境界標(杭や鋲)が存在するか確認
-
境界確定測量図の有無
-
境界が未確定の場合、売主に確定測量を依頼することが望ましい
境界が曖昧な土地は購入後に思わぬ費用(測量・交渉・訴訟)を要する場合があり、事前対応が必須です。
4. 越境に関する問題
建物や樹木、塀などが隣地に越境していないか、また隣地からの越境がないかを確認する必要があります。
-
越境がある場合、撤去や移設が必要になったり、隣地との覚書を交わさなければならない場合があります。
-
逆に隣地のものが越境している場合、将来的な紛争リスクを抱えることになります。
越境の有無は測量図や現地確認、場合によっては専門家(測量士・司法書士)の立会いによって調査することが重要です。
5. ローンの残債(抵当権)
中古住宅や土地を購入する際には、売主の住宅ローンの残債が残っている場合があります。
-
通常、売買と同時に残債を一括返済し、抵当権を抹消することが条件となります。
-
契約書に「引渡し時に抵当権を抹消すること」を明記し、抹消登記が確実に行われることを確認する必要があります。
-
残債が売買価格より多い場合(オーバーローン)には、追加資金の用意や金融機関との調整が必要になることがあります。
この点を疎かにすると、抵当権が残ったままの状態でトラブルに発展する可能性があります。
6. その他確認すべき重要ポイント
-
地盤・ハザード情報:地震や液状化リスク、浸水想定区域などを確認。
-
建築制限・用途地域:将来的な利用や増改築に影響するため、都市計画や用途地域、建ぺい率・容積率を把握する。
-
インフラ整備状況:上下水道・ガス・電気などのライフラインが整っているかを確認。
-
管理状況(マンションの場合):管理組合の運営状態、修繕積立金の残高、長期修繕計画の有無。
まとめ
不動産の購入においては、表面的な価格だけでなく、耐震基準・接道条件・境界線・越境問題・抵当権といった法的・物理的条件をしっかり確認することが重要です。これらを怠ると、将来的な利用制限や隣地との紛争、資産価値の低下といった大きなリスクを抱えることになります。
専門家(宅地建物取引士、司法書士、測量士など)に相談しながら慎重に進めることが、不動産購入を成功させる最大のポイントです。