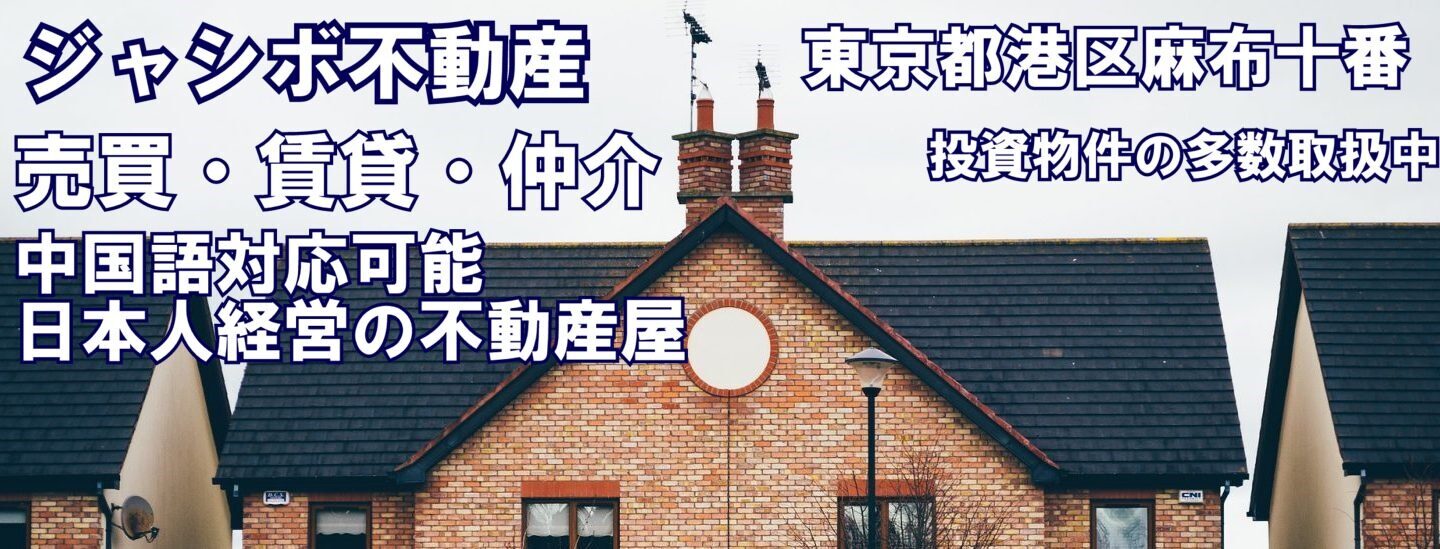相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続や遺贈によって取得した場合に課税される税金です。不動産は資産の中でも評価額が大きくなりやすく、相続税課税の中心となることが多いのが特徴です。特に日本では土地を所有している家庭が多く、現金よりも土地・建物の割合が高い資産構成であることが一般的です。
2. 不動産の相続税評価額の計算方法
(1) 土地の評価
土地の評価は、相続税路線価または固定資産税評価額を基に算出されます。
-
路線価方式
市街地における宅地は路線価に面積を掛けて評価します。
例:路線価30万円/㎡ × 100㎡ = 3000万円 -
倍率方式
路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に国税庁の定める倍率を掛けて算出します。
(2) 建物の評価
建物は、固定資産税評価額を用います。市場価格よりも低めの評価(時価の約70%程度)となるのが一般的です。
3. 不動産を相続する際の課題
(1) 分割しづらい
不動産は現金と違い分割が難しく、相続人間のトラブルの原因となりやすいです。
(2) 流動性の低さ
相続税納税のために現金が必要になりますが、不動産はすぐに売却できない場合が多く、納税資金の確保が課題となります。
(3) 維持費の負担
相続した不動産は固定資産税や管理費などの維持費がかかり、負担になるケースがあります。
4. 相続税対策の基本
相続税対策は大きく分けて3つの方向性があります。
(1) 評価額を下げる(生前の不動産活用)
-
貸家建付地の活用
土地に賃貸用建物(アパートやマンション)を建て、貸家として運用すると、土地評価額が約20%減額されます。 -
小規模宅地等の特例
居住用や事業用の宅地については、最大80%の評価減が受けられる特例があります(一定の条件あり)。
(2) 相続財産を減らす
-
生前贈与
毎年110万円までの贈与は非課税。長期的に行うことで財産総額を減らせます。 -
教育資金贈与・結婚資金贈与の特例
一定額まで非課税で贈与できる特例があり、相続財産を減らせます。
(3) 納税資金を確保する
-
生命保険の活用
生命保険金には500万円×法定相続人数までの非課税枠があり、相続税の納税資金としても有効です。 -
不動産売却・活用
相続前に不動産を売却したり、収益物件化して家賃収入を得ることで納税資金を準備できます。
5. 不動産を活用した具体的な相続税対策
(1) 賃貸マンション・アパート経営
賃貸用不動産は、土地評価額が貸家建付地として約20%減額され、建物も借家権割合(通常30%)により評価が下がります。
結果として、現金で持っているよりも相続税評価額を抑えられます。
(2) 土地の分割活用
1筆の大きな土地を複数に分筆して利用すると、評価額を抑えやすくなります。
また、相続人ごとに分けやすくなるため、トラブル防止にもつながります。
(3) 生前贈与と組み合わせる
収益不動産を子や孫に贈与しておくと、その後の家賃収入も子や孫に帰属することになり、相続財産の増加を防ぐ効果があります。
6. 小規模宅地等の特例(重要ポイント)
(1) 特例内容
-
居住用宅地(330㎡まで):評価額80%減
-
事業用宅地(400㎡まで):評価額80%減
-
貸付事業用宅地(200㎡まで):評価額50%減
(2) 適用条件
-
相続開始前に被相続人が居住・事業・貸付として使用していたこと
-
相続後も相続人が引き続き使用すること
7. 注意点
-
過度な節税スキームはリスク
不自然な不動産取引や極端な借入による節税スキームは税務調査で否認されることがあります。 -
維持管理のコスト
節税効果があっても、維持費や借入返済による負担が大きいと逆効果になることがあります。 -
専門家の関与が必須
税理士・不動産会社・司法書士など、複数の専門家に相談して計画を立てることが重要です。
まとめ
不動産は評価額が大きくなりやすいため、相続税の課税対象として非常に重要な資産です。しかし、特例を活用したり、不動産の活用方法を工夫することで評価額を抑えたり、納税資金を確保することが可能です。
特に、賃貸用不動産の活用や小規模宅地等の特例は効果が大きく、節税対策として広く利用されています。
一方で、無計画な節税対策はリスクが高く、将来のトラブルや資金負担を招く可能性があります。そのため、相続税対策は早めの検討と専門家のサポートが不可欠です。