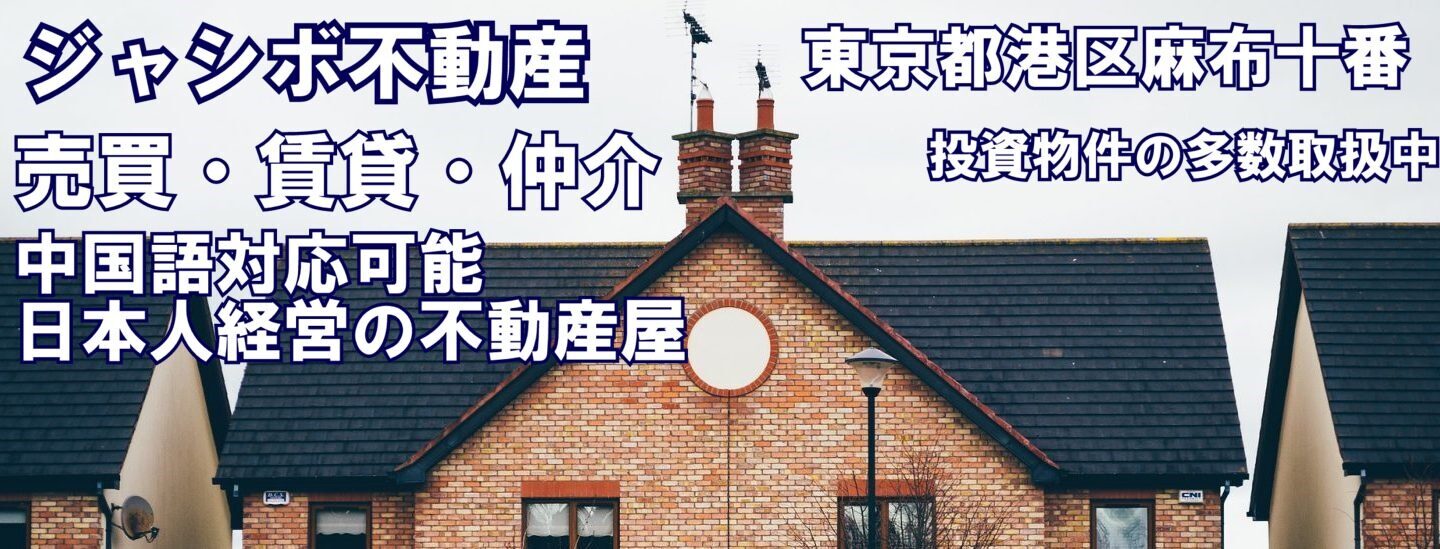1. 建蔽率(けんぺいりつ)とは
(1) 定義
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た水平投影面積)の割合を示します。
建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
(2) 目的
-
建物の敷地いっぱいの建築を制限し、防災・通風・採光を確保するため。
-
建物間に空地を確保し、火災時の延焼防止や避難通路を確保する役割があります。
(3) 法定建蔽率
都市計画で用途地域ごとに定められており、30%〜80%の範囲で指定されます。
例)
-
第一種低層住居専用地域:50%または40%
-
商業地域:80%
(4) 緩和規定
-
防火地域内で耐火建築物を建てる場合:+10%緩和(例:60%→70%)。
-
角地(2方向道路に接する敷地):+10%緩和。
2. 容積率(ようせきりつ)とは
(1) 定義
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積(建物全階の合計床面積)の割合を示します。
容積率(%)= 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100
(2) 目的
-
土地利用の高度化と居住環境の調和を図るため。
-
容積率を制限することで過密な建築を防ぎ、日照・通風を確保します。
(3) 法定容積率
都市計画により用途地域ごとに指定されます(100%〜1,300%)。
例)
-
第一種低層住居専用地域:100%または150%
-
商業地域:400%〜1,300%
3. 前面道路の幅員による容積率制限
(1) なぜ道路幅員で制限するのか
狭い道路に高層建築を建てると、交通や防災に支障をきたします。
そのため、前面道路の幅員が狭い場合、用途地域で定められた容積率よりも低い制限がかかります。
(2) 容積率の計算式
容積率(%)= 前面道路幅員(m) × 40(住宅系地域)または60(商業系地域)
※ その敷地の用途地域に定められた容積率と比較し、低い方が適用されます。
例1:住宅系地域(40倍ルール)
-
用途地域指定容積率:200%
-
前面道路幅員:4m
-
計算:4m × 40 = 160%
→ 適用容積率は160%(道路幅により制限)
例2:商業系地域(60倍ルール)
-
用途地域指定容積率:400%
-
前面道路幅員:5m
-
計算:5m × 60 = 300%
→ 適用容積率は300%(道路幅により制限)
4. 道路が複数ある場合
-
敷地が2つ以上の道路に接している場合、幅員が広い方の道路を基準に計算するのが原則です。
-
ただし、建物の主たる出入口が接している道路を基準にする場合もあります(自治体の判断による)。
5. 計算の実務
(1) 建蔽率の計算
-
敷地面積を確定(境界確定・測量必須)
-
用途地域の建蔽率を確認(都市計画図で確認)
-
角地・防火地域の緩和があるかチェック
-
計算例:敷地100㎡ × 建蔽率60% = 建築面積60㎡まで
(2) 容積率の計算
-
用途地域の容積率を確認
-
前面道路幅員による制限を確認(40倍・60倍ルール)
-
低い方を採用
-
計算例:敷地100㎡、道路4m、用途地域容積率200% → 道路制限160% → 延床160㎡まで
6. 不動産取引への影響
(1) 再建築時の制限
-
古家付き土地の購入時に、将来の建替えで建物規模が小さくなる可能性があります。
(2) 資産価値
-
建蔽率・容積率が高い土地は、より大きな建物を建てられるため資産価値が高い。
-
道路幅員が狭い場合、容積率制限で開発ポテンシャルが低下し、価格評価が下がることも。
(3) 開発計画
-
不動産開発業者は、道路幅員を広げる(寄付・セットバック)ことで容積率を引き上げ、事業性を改善する手法を取ることもあります。
7. 注意点
-
幅員の測定方法
-
境界から境界までの距離を計測(側溝も含めるかは自治体基準による)。
-
-
道路種別の確認
-
建築基準法上の道路でない場合は計算自体ができない場合あり(43条ただし書き道路)。
-
-
敷地形状
-
不整形地では、接道長や形状により有効建築面積が変わる。
-
-
緩和制度
-
防火・角地・高度利用地区などによる緩和・制限も併せて確認。
-
まとめ
-
建蔽率は敷地に対する建築面積の割合、容積率は敷地に対する延床面積の割合を制限し、都市環境や防災を考慮したルールです。
-
容積率は前面道路幅員による制限が大きなポイントであり、狭い道路では本来の容積率より低い数値が適用されることがあります。
-
不動産購入や開発計画の際には、用途地域と道路幅員を必ず確認し、将来的な建築可能規模を把握することが重要です。
-
投資家や事業者は、この制限を理解した上で、土地のポテンシャルを正しく評価し、資産活用戦略を立てることが求められます。